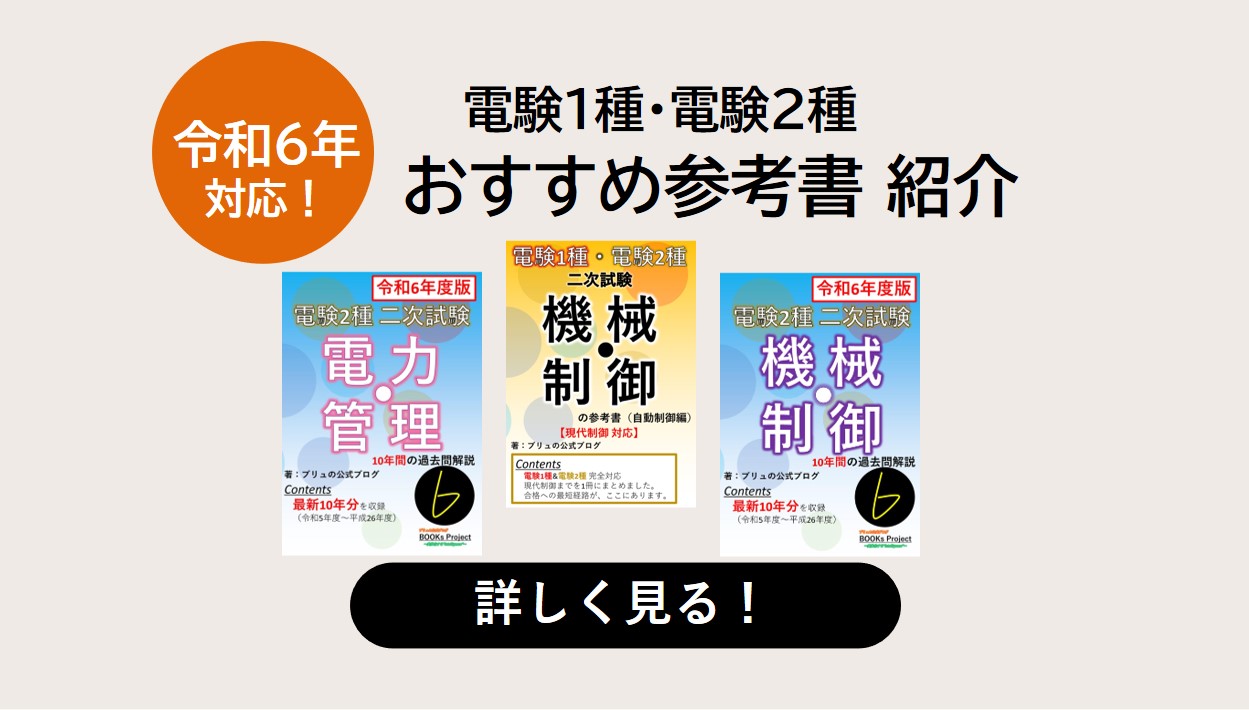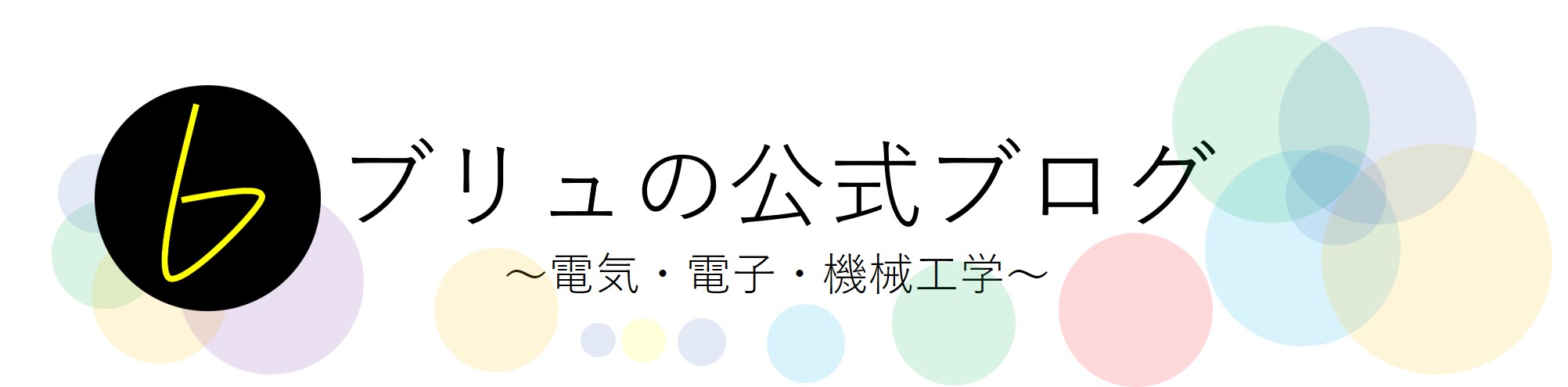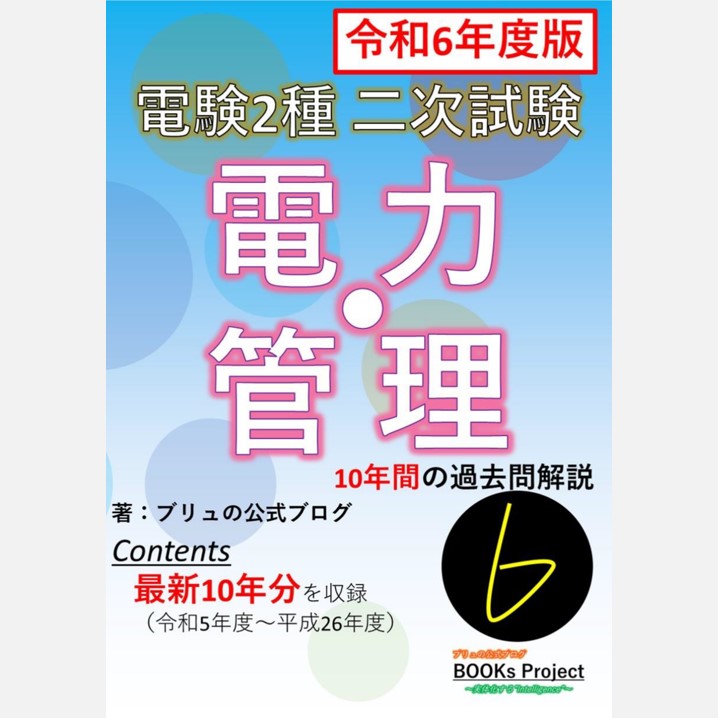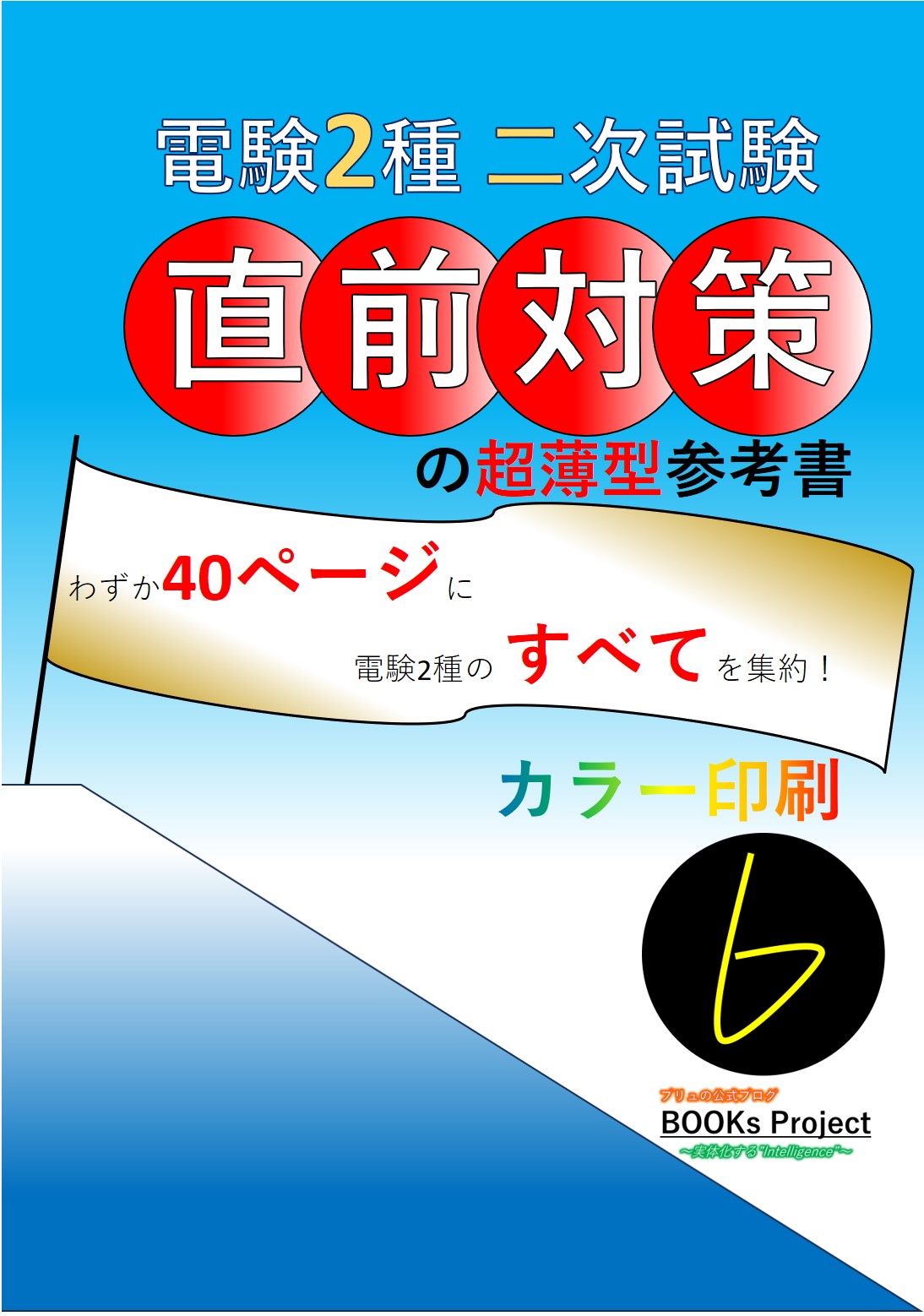みなさん、こんにちは!
ブリュの公式ブログ.org(for Academic Style)にお越しいただきまして、ありがとうございます!
この記事では、令和元年度 電験2種 2次試験 電力・管理 問6の過去問解説をします。
事業用電気工作物としての風力設備に関する論説問題です。
完全に法規の内容となるため、書けそうにない場合は避けるのが無難です。
令和元年度 電験2種 2次試験 電力・管理 問6
事業用電気工作物としての発電用風力設備に関して、次の問に答えよ。
(1)発電用風力設備は、公衆安全と電気保安の確保のために、設置時のみならず、巡視・点検等継続的に保守管理を行うことにより、運用中も「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」に適合するよう維持しなければならない。発電用風力設備において維持すべき重要な技術要件を二つ答えよ。
(2)風車が構造上安全であるために設計上考慮すべき風圧荷重を二つ答えよ。
(3)避雷塔や避雷針を施設する方法以外に、雷撃からブレードを保護する措置を答えよ。
(4)風力発電設備内部を雷撃から保護するために等電位ボンディングという方法が採用されている。この保護の方法について答えよ。
解答・解説
この問題の全体的な感想としては、小問(4)の等電位ボンディングは知っておくといいと思いますが、それ以外は完全に法規の内容です。
1次試験の記憶があれば回答できるかもしれませんが、2次の論説でこの内容について文章を書くのは、なかなか厳しいなと思います。
私が受験者だったら迷わず避ける問題です。
小問(1)
試験センター 標準解答
下記の内容から,二つの技術要件が記載されていればよい。
・危険表示や接近する恐れがないような措置など取扱者以外の者に対する危険防止措置を維持する。
・風車のハブ・ナセルの落下,ブレードの飛散などが発生しないように風車の構造上の安全を維持する。
・タワーの倒壊などが発生しないように風車を支持する工作物の構造上の安全を維持する。
・過回転時や制御機能喪失時の自動停止等により風車の安全な状態を確保する。
・雷撃防止措置等により風車の安全な状態を確保する。
・圧油装置等の危険の防止を図る。
など
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」で以下の内容が定められています。
省令 第3条
風力発電所を施設するに当たっては、取扱者以外の者に見やすい箇所に風車が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
省令 第4条
風車は、次の各号により施設しなければならない。
一 負荷を遮断したときの最大速度に対し、構造上安全であること。
二 風圧に対して構造上安全であること。
三 運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。
四 通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。
五 運転中に他の工作物、植物等に接触しないように施設すること。
省令 第5条
第五条 風車は、次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。
一 回転速度が著しく上昇した場合
二 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合
省令 第7条
第七条 風車を支持する工作物は、自重、積載荷重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造上安全でなければならない。
小問(2)
試験センター 標準解答
・突風や台風等の強風による風圧荷重のうち最大のもの
・風速及び風向の時間的変化により生じる変動荷重
終局荷重と疲労荷重
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の解釈 第4条で、以下の記載があります。
①終局荷重
風車の受風面の垂直投影面積が最大の状態における最大風圧
→突風や台風などの強風による荷重のこと。ただし、故障などでヨーが制御できないなど、風車の回転面が制御できない状況であっても強風に耐えられなければなりません。
②疲労荷重
風速及び風向の時間的変化による風圧
→風車への風速や風向の時間的変化によって生じる荷重変動のこと。ボルトや溶接部分は疲労がたまりやすいので、累積疲労にも耐えられる必要があります。
小問(3)
試験センター 標準解答
設置場所の落雷条件を考慮して,レセプターを風車へ取り付ける及び雷撃によって生じる電流を風車に損傷を与えることなく安全に地中に流すことができる引下げ導体等を施設する。
風力発電の雷撃対策
解釈 第7条に、以下の記載があり、この内容に沿ったものを解答すればOKです。
■解釈 第7条 抜粋
6 省令第5条第3項に規定する「雷撃から風車を保護するような措置」とは、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
一 発電用風力設備を設置する場所の落雷条件を考慮し、レセプターの風車への取付け及び雷撃によって生ずる電流を風車に損傷を与えることなく安全に地中に流すことができる引下げ導体等を施設すること。
二 風車を支持する工作物(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の高さが 20 メートルを超える部分を雷撃から保護するように、次に掲げる要件の全てを満たす避雷設備を設けること。
イ 雷撃によって生ずる電流を風車を支持する工作物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備として、日本工業規格A4201(建築物等の雷保護)―2003に規定する外部雷保護システムに適合する構造であること。
小問(4)
試験センター 標準解答
風力発電設備内部の離れた導電性部分間を直接導体又はサージ保護装置で電気的に接続することで,その部分間に雷電流により発生する電位差を低減させて保護する。
等電位ボンディング
等電位ボンディングとは、建物の電位差を0にする設置方法のことを言います。
解図1は等電位ボンディングされていないとき、避雷針に雷撃があったときの雷電流の流れを示しています。
この時、避雷針直下の接地極に大量の電流が流れることで、接地極間に電位分布が生じます。

解図1 避雷針への雷撃と接地極間の電位分布
解図2に示す通り、電流は高電位から低電位へ流れるため、この接地極間の電位分布によって、他の接地極から電流が逆流し、機器の破損につながる可能性があります。

解図2 接地極から所内への電流の逆流
そこで解図3のように、接地極間の電位分布が生じないように設置すれば、電流の逆流は生じません。
これを等電位ボンディングといいます。

解図3 等電位ボンディング
おすすめ参考書
Amazonで参考書を販売しています。
価格:2,490円
内容:重要公式が一目でわかる、40ページでまとめた参考書。
フルカラー印刷。
時短にもなる、電験2種 二次試験の必携参考書です。