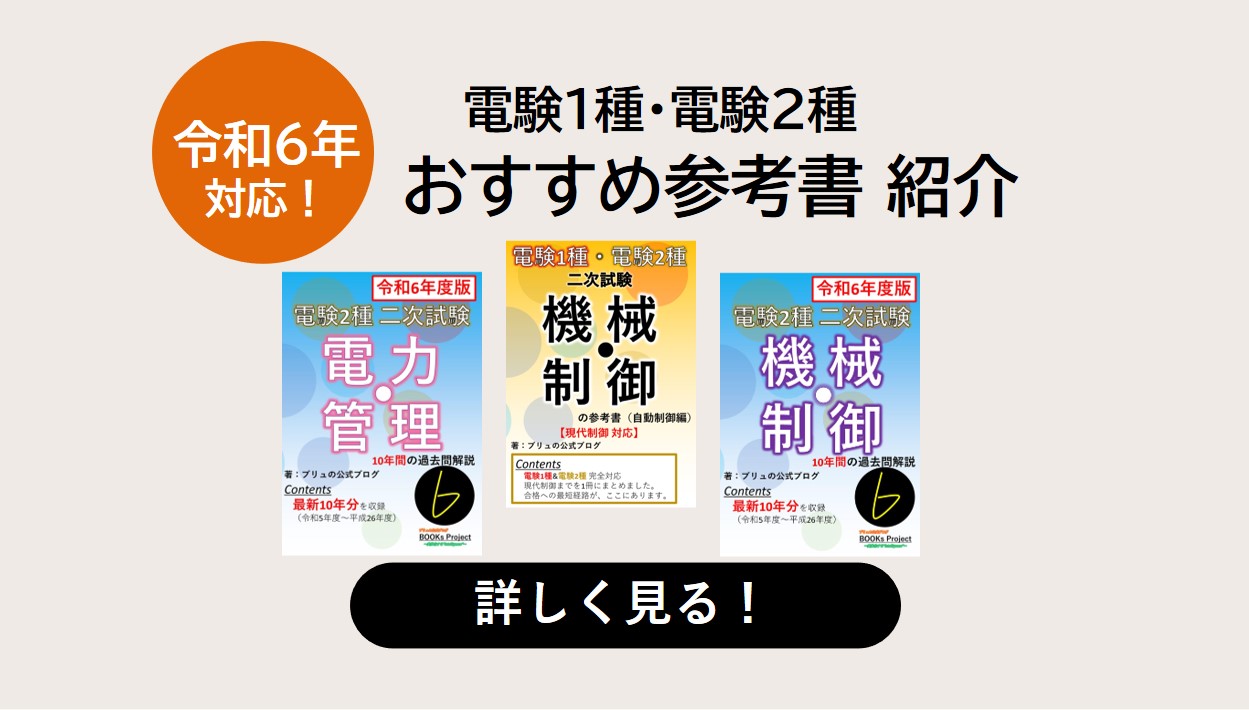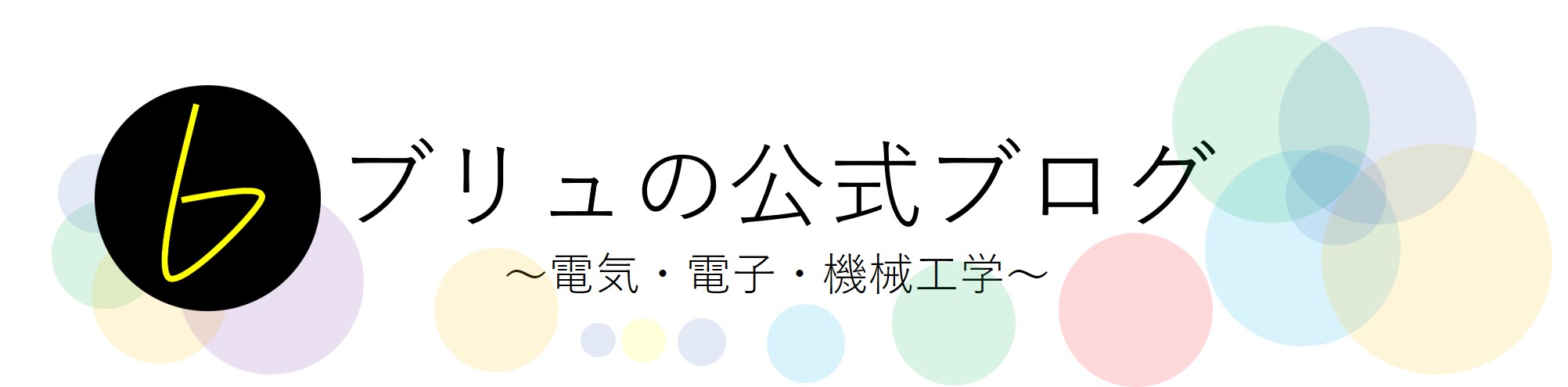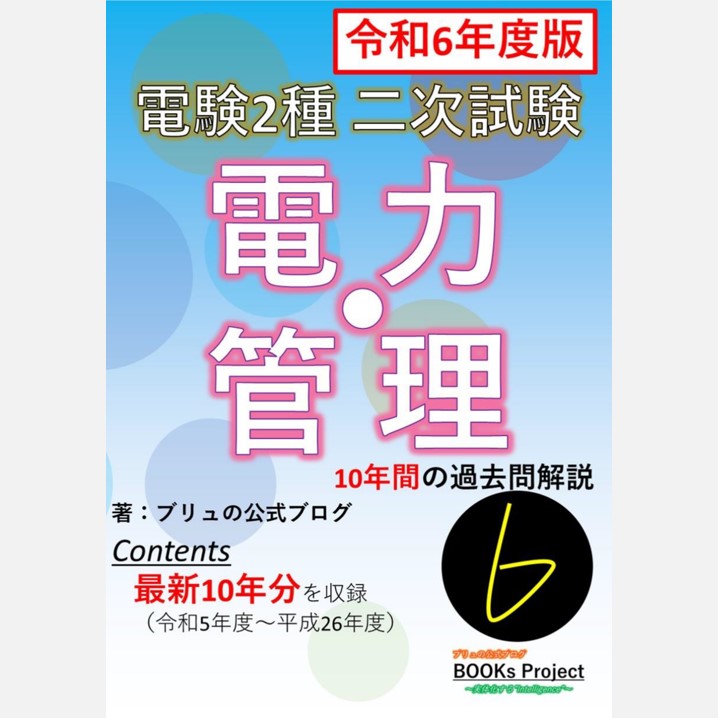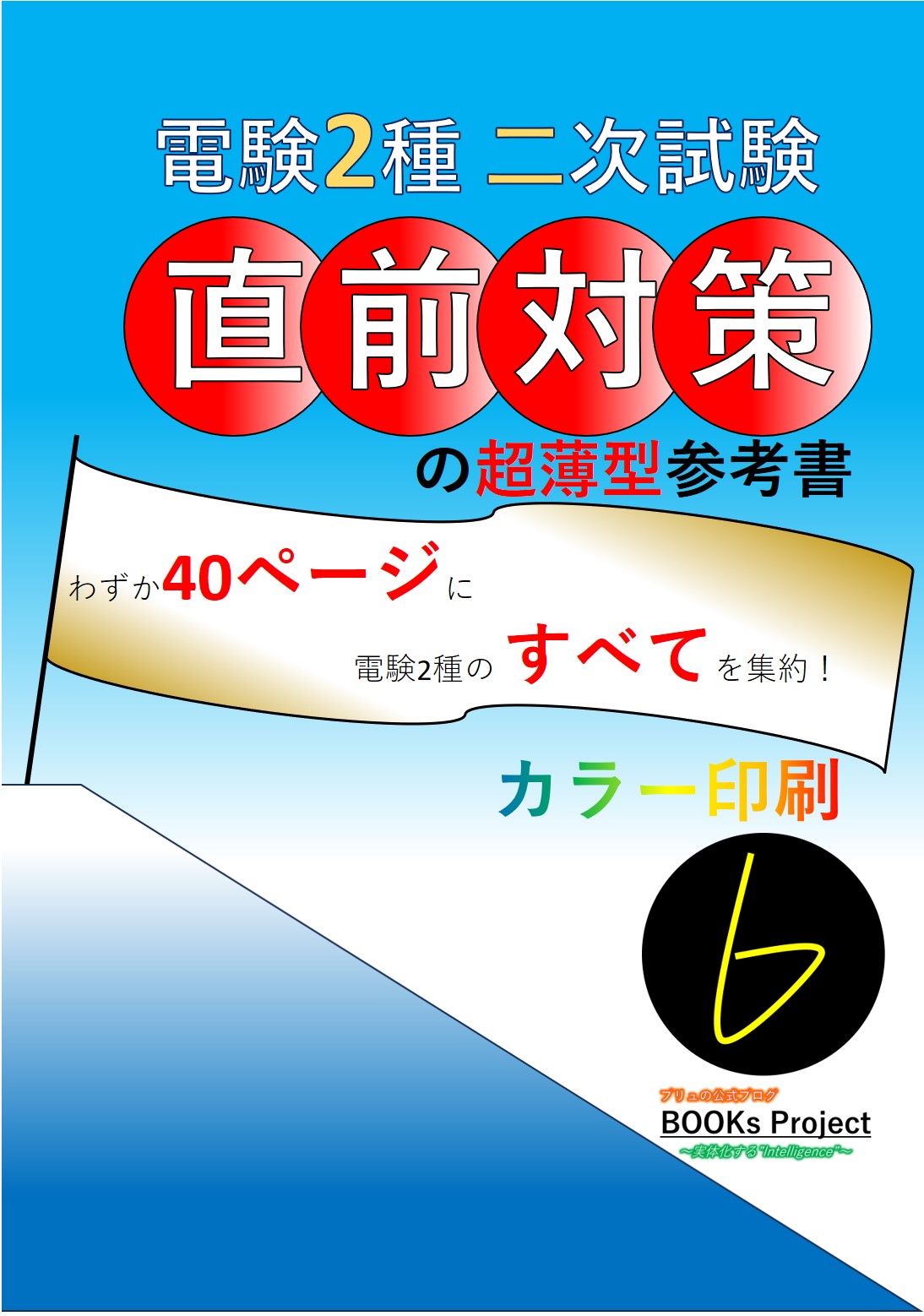この記事では、令和4年度 電験2種 二次試験 電力・管理 問2の過去問解説をしています。
出題内容としては、変電所の避雷器と課電率に関する論説問題で、変電所に避雷器を設置するときの注意点や、酸化亜鉛素子の非線形特性に関する基本的な論説問題になっています。
令和4年度 電験2種 二次試験 電力・管理 問2
電力系統には雷撃や系統運用における過渡現象などにより異常電圧が発生することがあり、電気施設の絶縁保護を目的に、変電所等に避雷器が設置される。近年は、特に、保護特性の優れた、直列ギャップを使用しない酸化亜鉛(${\rm ZnO}$)を主成分とした酸化亜鉛形避雷器(ギャップレス避雷器)が多く使用されている。変電所に設置される酸化亜鉛形避雷器(ギャップレス避雷器)について、次の問に答えよ。
(1)変電所における避雷器の設置上の留意点及びその理由を100字程度以内で述べよ。
(2)酸化亜鉛形避雷器(ギャップレス避雷器)の特徴を三つ挙げ、それによるメリットも含めてそれぞれ50字以内で述べよ。
(3)酸化亜鉛形避雷器(ギャップレス避雷器)では、保護レベルと機器寿命の関係を定量的に表すのに、常時連続的に印加される電圧ストレスの大きさを示す課電率(通常、連続使用電圧/動作開始電圧)を用いる。そこで、課電率による保護レベル設定と機器寿命の関係について80字程度以内で述べよ。
解答・解説
小問(1):避雷器の設置上の留意点及びその理由
(試験センター 解答)
以下の避雷器の設置上の留意点及びその理由から一つ記載されていればよい。
・避雷器は線路引込口や極力被保護機器に近く設置する(約 50 m 以下)ことが望ましく,距離があまり遠くなると被保護機器の端子に加わる異常電圧の値は避雷器の制限電圧に比べて高くなり,これを設置した効果がなくなる。
・避雷器と大地間の接地線は極力接地抵抗(インピーダンス)を小さくし,高周波サージに対するインダクタンスを抑えることで,避雷器-大地間の電圧上昇により保護レベルに影響をおよぼさないようにする。
避雷器の特性について
避雷器には、解図1(a)に示すように、${\rm SiC}$を特性要素としたギャップ付きの避雷器と、(b)に示すように${\rm ZnO}$によるギャップレスの避雷器が存在します。
 (a)ギャップ付き避雷器(${\rm SiC}$) |
 (b)ギャップレス避雷器(${\rm ZnO}$) |
解図1
避雷器は、解図2に示すように、非線形な電流-電圧特性が求められます。
黒線で示す通り、理想的には制限電圧以下では電流は流れず、制限電圧に達した瞬間に瞬時に大電流を流す特性です。
従来、避雷器には、解図1の青で示す、${\rm SiC}$+ギャップによって非線形性を実現していました。しかし、赤線で示すようにギャップレスの${\rm ZnO}$(酸化亜鉛素子)が登場し、
- より理想的な特性に近いこと
- ギャップがないため耐汚損性に優れること
がメリットとなり、最近では${\rm ZnO}$が採用されています。
そのほか、正常時に常規対地電圧が印加された時、避雷器を通して大地に流出する電流を漏れ電流といいますが、これは小さい方が望ましく、解図2から明らかなように、この点においても${\rm ZnO}$の方が優れています。

解図2
避雷器の距離について
避雷器は保護対象機器に近い位置に設置することが必要で、おおよそ50m以内とされています。
避雷器は、雷サージなどの異常電圧が印加された時、避雷器の設置しているその地点での電圧を制限電圧にまで抑え込みますが、避雷器から離れた位置までは電圧を抑えることができないので、こうした距離の規制があります。
イメージとしては、解図3に示すように、避雷器と保護対象機器の距離が近ければ機器は保護されますが、遠ければ異常電圧から保護できない可能性があります。
 (a)保護できるとき |
 (b)保護できないとき |
解図3
小問(2):酸化亜鉛形素子(ギャップレス避雷器)の特徴とメリット
(試験センター解答)
以下の酸化亜鉛形避雷器の特徴とメリットから三つ記載されていればよい。
・直列ギャップがないため放電電圧-時間特性に関係する課題がなく,機器絶縁に対する保護レベルが向上する。
・微小電流から大電流サージ領域まで高い非直線抵抗特性を有することで過電圧を抑制することができる。
・素子の単位体積当たりの処理エネルギーが大きいので,従来に比べ寸法の小型化と構造の簡素化が実現できる。
・並列素子数を増加することにより,許容される吸収エネルギーの増加が図れ,サージに対する耐量が向上する。
・無続流のため,多重雷などに対する動作責務に余裕があり温度上昇が少なく,機器の長寿命化が期待できる。
・降雨等による汚損及び洗浄時の不均一電位分布などの問題がなく,局部アークの発生を抑制することができる。
保護レベルの向上と不均一電位分布・局部アークの発生の抑制
解答例の1個目と6個目に相当します。
${\rm ZnO}$のメリットを考えていくのもいいですが、${\rm SiC}$+ギャップのデメリットを考え、それが${\rm ZnO}$のデメリットに当てはまらなければ、それが${\rm ZnO}$のメリットになります。
さて、ギャップがあれば、その放電特性は周囲の環境に依存します。解図4に示すように、湿気が多く水分が付着していたり、空気中のちりが多くゴミが付着していたりする場合があります。
水分が多ければ放電特性に影響が出ますし、ゴミが付着していればギャップの電界分布が不平等になり、やはり放電特性に影響します。
 (a)直列ギャップに水分が付着する例 |
 (b)直列ギャップにゴミが付着する例 |
解図4
その点、ギャップレスの${\rm ZnO}$についてはこうした周囲の環境の影響を受けないので、その点がメリットとなります。
ここでも余談ですが、変電所の絶縁や遮断器の話のときに、${\rm SF_6}$ガスというものも登場します。
この${\rm SF_6}$ガスの放電開始電圧は空気の3倍程度あり、さらに人に対して無害である夢のような気体です。
欠点として、放電後に分解物が生成されてしまったり、地球温暖化に関係してしまうガスなので取り扱いには注意が必要ですが、非常に取り扱いやすいガスといえるでしょう。
しかし、不平等電界によって絶縁耐力が大幅に低下します。
このように、電気関係において、不平等電界は非常に弱いイメージを持っておくといいでしょう。
ギャップへのゴミの付着、特に金属粉などはNGです。
高い非線形抵抗特性
回答例の2個目に相当します。
これは${\rm ZnO}$の特性そのものです。解図2で示した通り、避雷器に求められる理想的な特性に対して、${\rm ZnO}$の方が優れているので適任ということになります。
小型化と構造の簡素化
回答例の3個目に相当します。
${\rm ZnO}$はギャップが不要なので、非常にコンパクトな避雷器になります。
吸収エネルギーの増加とサージに対する耐量の向上
回答例の4個目に相当します。
並列に接続することでサージを処理するエネルギーが分散されるので耐量が向上します。
特に雷サージを大地に逃がす際に熱が発生するので、並列接続することでその熱を分散し、信頼性を向上させたり、避雷器全体としての吸収エネルギーの増加を行えたりします。
さて、余談ですが、酸化亜鉛素子も単位動作責務(雷サージを大地に逃がし、放電電流を流した後、続流を遮断し正常な状態に復帰する一連の動作)を繰り返すことで、徐々に壊れていきます。
そして、ある限界点を超えてしまうと、雷サージを逃がすときに生じるZnOの発熱量が、空気中への放熱量を上回ることとで熱暴走を起こし、完全に破壊されます。これを防ぐために、安定性評価が行われています。
無続流
回答例の5個目に相当します。
ZnOはギャップがなく、放電を行わないので、雷サージが通過した後はすぐに大地への電流を遮断し、通常状態に復帰します。すなわち無続流になります。
続流のイメージを解図5に示します。異常電圧になると避雷器を通じて電流が大地に流れますが、異常電圧が過ぎ去った後に、ダラダラ電流が大地に向けて流れるのか、ピタッと止まるのかのイメージをつかんでください。
 (i)異常電圧時 |
 (ii)続流 |
| (a)SiCの場合 | |
 (i)異常電圧時 |
 (ii)無続流 |
| (b)ZnOの場合 | |
解図5
小問(3):課電率による保護レベルと機器寿命
(試験センター解答)
・課電率を高くすることで,保護レベルを低く設定でき,絶縁設計の合理化が実現できるが,機器寿命が短くなるためこの経済バランスを考慮した仕様検討が必要となる。
課電率とは
課電率について、
$${\rm 課電率}=\frac{{\rm 連続使用電圧}}{{\rm 動作開始電圧}}$$
であるので、課電率が高ければ、連続使用電圧と動作開始電圧の値が近くなることがわかります。
そのため、ちょっとしたサージ電圧でもすべて避雷器が大地に流してくれるので、保護対象の機器の保護レベルは低く設定でき、合理的になります。
一方で、避雷器には通常時においても漏れ電流が流れており、課電率が大きければ漏れ電流も大きくなってしまうので、避雷器の劣化は早くなります。
避雷器の劣化と保護レベルの低下、この2つの面を考慮して、できるだけ低コストできる使用検討が必要になります。
おすすめ参考書
Amazonで参考書を販売しています。
価格:2,490円
内容:重要公式が一目でわかる、40ページでまとめた参考書。
フルカラー印刷。
時短にもなる、電験2種 二次試験の必携参考書です。